造園業に興味があるけれど、どうやって始めればいいのかわからない——そんな声はよく聞きます。実際、造園の世界に飛び込む入り口は一つではありません。もっとも多いのは、地元の造園会社に「未経験歓迎」の求人で応募するパターンです。アルバイトからスタートして、仕事を覚えながら正社員になる人も多く、必ずしも経験や資格が必要なわけではありません。
また、公共職業訓練校や専門学校を経由して造園業界に入る人もいます。こうしたルートでは、基礎的な知識や技能を学べるため、職場での理解も早まりやすいという利点があります。一方で、ハローワークを通じた求人紹介や、建設関係の紹介サイトから入職するケースも一定数あります。大事なのは、自分の生活スタイルや目的に合った入り口を見つけることです。
2級造園施工管理技士はいつ必要になる?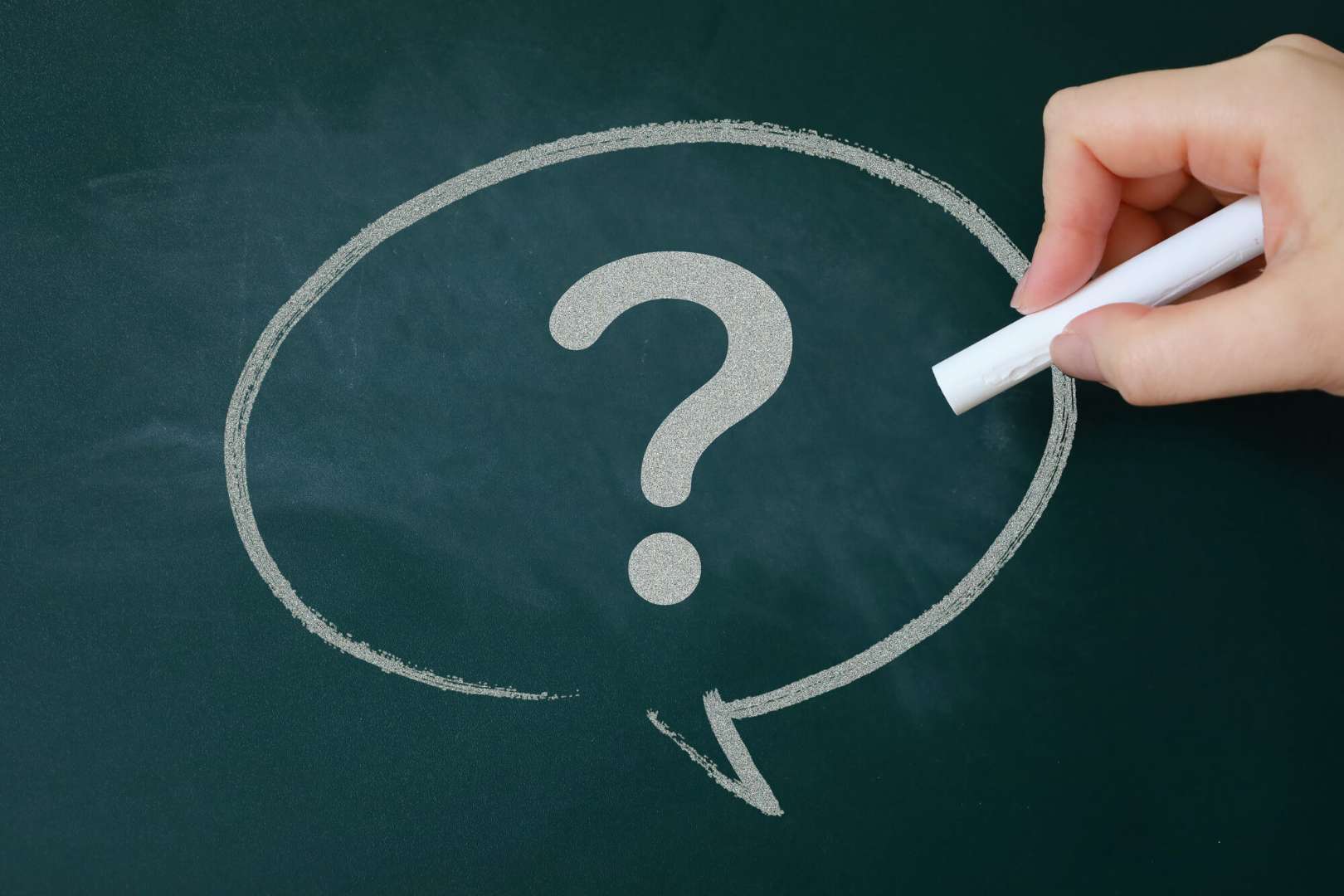
未経験から造園業を始めるにあたって、「資格がないと採用されないのでは?」と不安に思う人もいるかもしれません。でも実際のところ、入職時点で資格が必須というケースはほとんどありません。多くの造園会社では、「見習い」や「補助作業員」としてのスタートが一般的で、仕事を覚えながら、徐々にステップアップしていく仕組みになっています。
ただし、キャリアを長く続けていくうえで、資格は確実に武器になります。とくに注目されるのが「2級造園施工管理技士」。これは、現場の責任者として工事を管理するための国家資格で、一定の実務経験を経たうえで受験が可能になります。たとえば、高卒で造園業に就いた場合、3年以上の実務経験があれば受験資格が得られます。
この資格を取得すると、現場での役割が広がるだけでなく、給与や待遇にも反映されるケースが多くなります。また、公共工事などでは施工管理技士が現場に配置されていることが求められるため、会社にとっても重要な人材と見なされるようになります。逆に言えば、資格を持っていないうちは「手を動かす人」、持っている人は「現場を動かす人」という立ち位置に分かれるとも言えます。
初めは無資格でも構いませんが、「いつかは責任のある立場になりたい」と考えるなら、働きながら資格取得を目指せる職場環境かどうかは、会社選びの大きなポイントになります。
30代・40代からでも遅くない?リアルな年齢事情
「もう若くないけど、今からでも間に合うだろうか」——これは造園業界への転職希望者からよく聞く声です。たしかに、肉体労働のイメージが強いため、年齢に不安を感じるのも無理はありません。でも実際には、30代や40代から未経験で飛び込む人も少なくありません。中には50代で入ったという人もいます。
造園業界は慢性的な人手不足に悩まされており、年齢よりも「やる気」や「素直さ」を重視する会社が多いのが実情です。とくに、きちんと挨拶ができる、真面目に取り組む、周囲と協力できる——こうした基本的な姿勢が評価される傾向があります。これは、年齢に関係なくチャンスがある業界とも言えるでしょう。
ただし、体力的な壁がまったくないわけではありません。夏の暑さ、冬の寒さのなかでの作業は若手でも厳しいものです。自分のペースを把握し、無理せず続けていける環境を選ぶことが重要です。また、年齢を重ねている分だけ、素直に教えを受けられるかどうかも大きなカギになります。「年上なのに新人」という立場を気にしすぎず、学ぶ姿勢を大事にできるかが問われます。
学歴についても、造園業ではほとんど問われることはありません。むしろ現場では、どれだけ周囲と協調できるか、どれだけ丁寧に作業できるかが評価される場面が多いです。過去の経歴よりも、「これからどう働きたいか」をしっかり考えている人のほうが、長く続けられる傾向があります。
新人のうちは「掃除と運搬ばかり」って本当?
未経験で造園業に入ると、最初に任されるのは「いかにも職人らしい仕事」ではなく、地味な作業がほとんどです。たとえば、現場の清掃、資材の運搬、刈った枝葉の片づけなど。「掃除ばかりでつまらない」と感じる人もいるかもしれませんが、これらは決して軽んじていい仕事ではありません。
造園現場は限られたスペースの中で多くの作業が同時進行します。そこに資材やゴミが散らかっていると、転倒や事故の原因になります。つまり、掃除や整頓は安全管理の第一歩。これをきちんとできる人は、現場からも信頼されやすいのです。
また、運搬作業も重要です。石材や苗木、工具など、正確に素早く届けることができれば、作業の流れを止めずに済みます。職人たちはそうした小さな気配りを見ていて、次に剪定の補助や芝張りといった作業を少しずつ任せてくれるようになります。
「早く道具を握りたい」「木を切ってみたい」と焦る気持ちもあるでしょう。でも、こうした補助業務の中にこそ、造園の基本や段取りの流れが詰まっています。見て覚える、手を動かして体で理解する——そうやって積み上げた経験は、あとで確実に活きてきます。
自分がどの作業にも「意味を見つけられるか」。それが、長く続けていく上での分かれ道にもなります。見澤園では、こうした基本から丁寧に学べる職場環境を整えています。興味のある方は、まず採用ページをご覧ください。
→ https://www.misawaen.jp/recruit
ブラックを避けて「学べる職場」に出会うには
造園業界に限ったことではありませんが、働きはじめる会社によって、職場環境は大きく異なります。「体力勝負だけで丁寧に教えてくれない」「人間関係がきつくて続けられない」といったケースも残念ながら存在します。では、どうやって良い職場を見極めればよいのでしょうか。
ひとつの手がかりは、「教育体制があるかどうか」です。未経験者に対して、段階的に教える仕組みがある会社は、育成に力を入れている証拠です。求人情報に「丁寧に教えます」と書かれていても、具体的にどう教えるのかが曖昧な場合は、実態が伴っていないこともあります。
また、社員の年齢層も見極めのヒントになります。20〜30代が多い現場は、比較的風通しがよく、未経験者への理解もある傾向です。逆に、年齢層が高すぎる場合は、新人が入りにくい雰囲気になっている可能性もあるので、事前に確認できると安心です。
もうひとつは、現場の働き方。たとえば、「毎日直行直帰できるかどうか」「残業が多いかどうか」なども、実は大きな違いになります。家庭との両立や、健康面を考えるうえでも、長く続けられる条件かどうかは必ずチェックしておきたいところです。
可能であれば、事前に見学や職場訪問を申し込んでみると、求人情報からは見えない現場の雰囲気もつかめます。「ここなら続けられそう」と思えるかどうか、自分の感覚を大事にしましょう。
始めることより、続けることを大事にしよう
造園業に入る方法はいくつもありますが、本当に大事なのは「どう始めるか」ではなく「どう続けていくか」です。最初は右も左もわからないのが当たり前。それでも、一つひとつの作業に意味を見出しながら、コツコツ続けることが、やがて一人前の職人へとつながっていきます。
資格も、キャリアも、焦る必要はありません。まずは現場のリズムに慣れ、自分の体と気持ちで「この仕事、悪くないな」と思えるかどうか。そこから次の一歩を考えれば十分です。
もし迷いや不安があるなら、一度相談してみてください。現場の空気を感じるだけでも、答えは変わってくるかもしれません。


